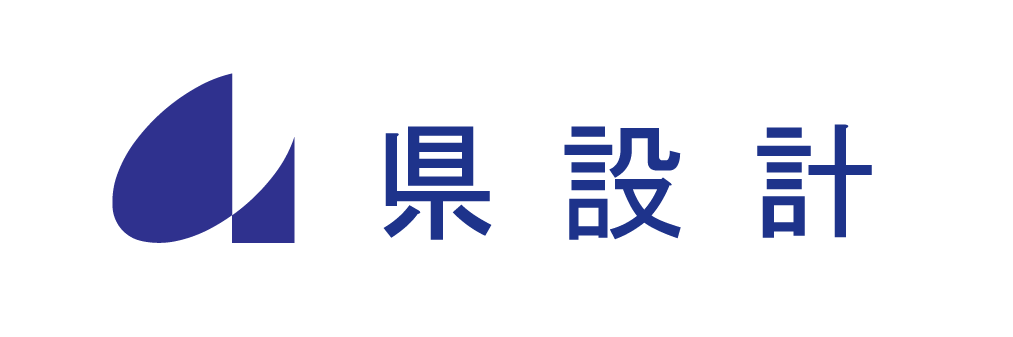第一稿で名前を出した三島由紀夫について 大槻
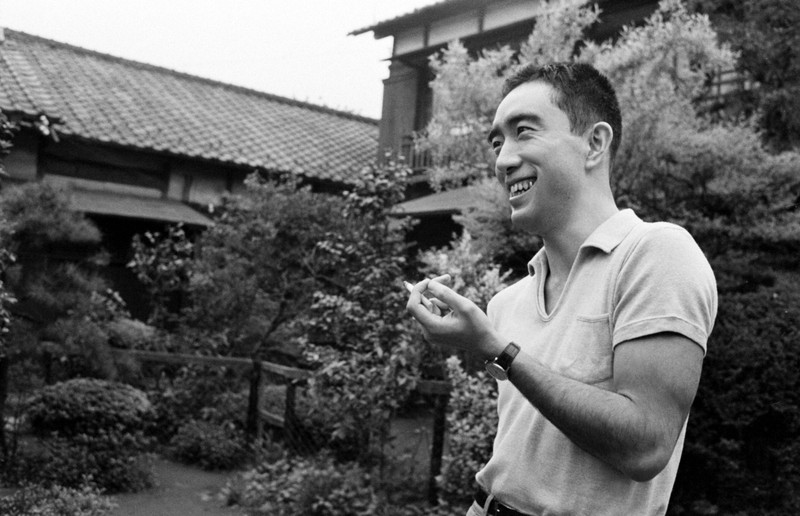
自宅の庭でくつろぐ作家の三島由紀夫=東京都目黒区で1958年4月、納富通撮影 毎日新聞社より引用(https://mainichi.jp/articles/20250114/k00/00m/040/325000c)
三島由紀夫のあの行為について何と呼べば適切か、今も決めかねている。事件、という人もいるし割腹自決した日、という人もいる。今は確か「憂国忌」という季語になっていると思う。
昭和45年11月25日、当時私は25才であった。三島と20才違う。その時東京の百貨店で三島の展覧会が模様されていて話題になっていた。私は本が好きでよく読んでいたが、いわゆる文学者の書く小説にはあまり関心がなかった。ミステリー、当時の言い方をすれば“探偵小説あるいは推理小説”とかUFO(当時は空飛ぶ円盤と言っていた)といった類の本ばかり読んでいた。
三島に関心を持ったのはその事件以降である。「なぜ彼は腹を切ったのかあるいは切らざるを得なかったのか」という疑問で。三島が凄いのは1年くらい前から11月25日を決めていたことである。かつて私は三島がその行為をする瞬間「なぜ俺はこんなことをしなければならないのか」と疑問に思ったに違いないと考えていた。はたして。
当日、三島は予定の行動をして割腹した。この時を想定して腹筋を鍛えていた。鍛えすぎて筋肉が締まり過ぎ刀が抜けなくなった。楯の会の森田(同じ日に自決した)が介錯することになっていたのだが2度失敗して結局楯の会のもう一人が三島と森田の介錯をした。
ちなみに人を切るには剣道のほか居合を習得する必要がある。首かどこかを刀の背でたたき、一瞬あごが上がったところを落とすのだそうだ。
切腹の仕方を父から教わったことがある。腹を切るとひっくり返るから尻に二枚に折った座布団を敷き前かがみに座る。刀を横にひいて最後少し切り上げる。これが十文字に掻っ捌いて、ということだと。介錯する人がいない場合は、刀を引き抜いて頸動脈を切る。三島は映画などで散々練習をしたはずであるが計画通りにいかないこともある。
事件後、人々は生前彼が言っていたことは本気だったのだと思い知った。その言動も本物になった。私も目立ちたがりの流行作家と思っていたのだが以降、今に至るまで関心の一番の対象となっている。55年もの間。
三島はかわいそうな人である。その運動神経のなさを石原慎太郎に散々バカにされた。剣道は五段か何かで「今度は錬士をとる」とか言っていたそうであるが、振りあげた竹刀を下ろして止める時の絞りが全くできなかったそうだ。剣道は素振りから始めるが「雑巾を絞るように」と最初に教わることである。
石原との対談の後、部屋で刀を抜いたが鴨居か何かに刺さってしまい動きが取れず「私の方が勝つ」とか言われたとか、映画に出たときカードか何かを投げる場面がうまくゆかず、何十回もNGを出されたとか。
評論家と実務家の違いは、設計しているときに「あの人が設計したのはこんな意味があったのだ」と感じることがある。まれにではあるが。評論家にはそういう体験はない。この三島と石原の話も互いに認めあっていてそのうえで、という話である。
ここは設計事務所のコラムであるからそれらしいことを書くと、三島の書いた本の中で文学、とか小説とかの単語を建築、という単語に置き換えるとそのまま建築論になる本があった。手元にある「文章読本」や「小説とは何か」を見てみてもそれらしい表現がないので別の本であろう。物を造像する人の発想は表現方法こそ違っても同じかなと思う。
先ほどの答えを言ってしまうと、石原の「三島由紀夫の日蝕」に書かれていることが一番回答に近いと思う。次は最近読んだ西尾幹二の「三島由紀夫の死と私」か。万が一この文章で三島に関心を持った人にはどうか最後に読んでほしい、と思うのであるが。

三島の最後の作品は輪廻転生をテーマにした「豊饒の海」である。脱稿の日付と同じ11月25日は三島の誕生日の49日前、と指摘したのは小室直樹である。
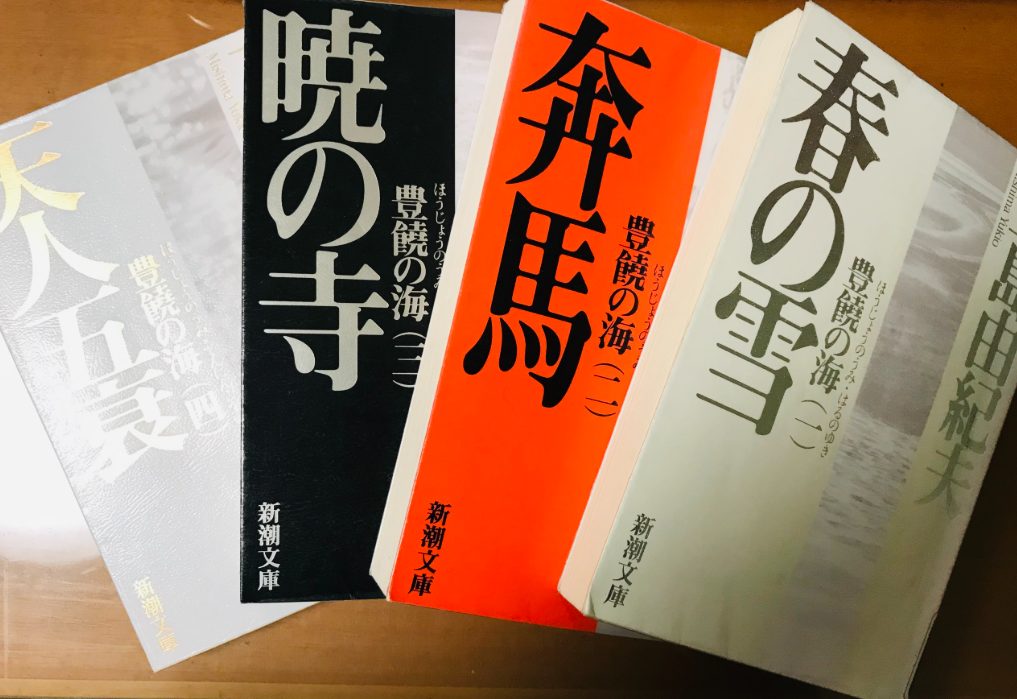
蛇足ではあるが、この事件で男と女は全く別な生き物、と感じたことがある。男どもは「三島は文学に行きづまってあの行動に出た」とか「政治的な意味は」とか行動をおこした理由を求めたのだが(私も同様である)ある女性作家は、「かわいそうに、一人の男があんなに一所懸命に話をしているのに聞き取れない。誰かマイクを持って行って」と。母性であろうが発想の次元が全く違っていた。