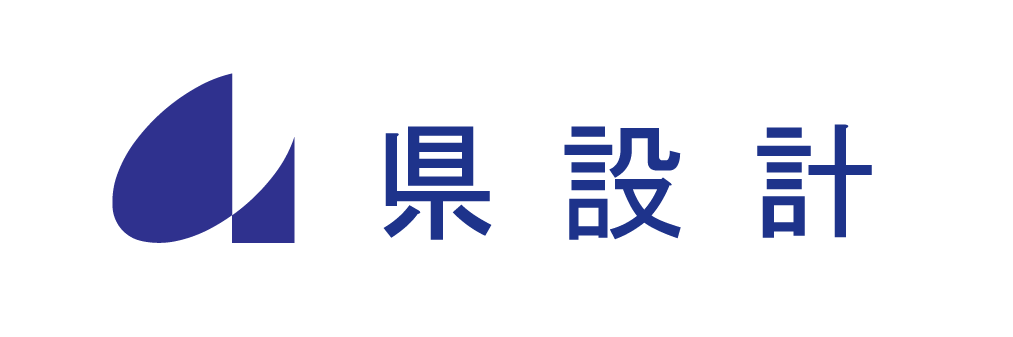私の材料の選び方 大槻
表記についてなにか書けと言われて。
若いころ(20代半ば)影響を受けた人がいる。深澤正二という人で、奥さんが私の遠い親戚筋、本人は山男たちから「唐沢天皇」と言われていた人。冬以外は河童橋から見える唐沢の岩小屋に住んでいて、冬は爺ケ岳でスキーだけをしていた人だった。小さい頃、当時は珍しかったスライドで唐沢の植物などを教えてもらった。チングルマという名前を覚えたり、また長寿の薬だとか言ってコケモモのジャムを祖父がもらったりしたこともあった。
そんな彼がファンの一人となっている奥田郁太郎という画家がいた。
安井曾太郎らが創設した「一水会」の最高賞をとったほどの人だったが、中央の商業化された画壇になじめず信州に来て絵だけを描いていた。生活を、と言っても三食と少量の酒と風呂だけであるが、するために号二千円(だけ)で愛好家に絵を分けていた。
深澤さんが奥田さんの話をする中で「売り絵を描かない本物の画家」という言い方をしていた。「絵描きは展覧会で絵の買い手が何人かいたら、売るために同じ絵を何枚も描く」しかし奥田さんは違うのだと。(冷めた言い方をすると、例えば宮廷画家などは押しなべて売り絵しか描いていないのだが。まあ当時は画家という職業はなく、絵を描く職人だったとも言える)そして絵描きは毎日デッサンを描いて修行をしていると。そこで私が「設計を志す者は毎日何を考えて修行すればいいか」と聞いた。彼はまさか私からそんな質問があるとは予想していなかった。そしてしばらくして「毎日、何が本物であるかを考えること」と答えた。
設計の何たるかも知らず、とっさに考えついたことには違いなかったはずだが妙に印象に残っている言葉である。蛇足であるが「一水会」は遠・中・近と言って風景を描く時に遠景、近景、そしてその中間の景色を描いて奥行き感を出すのだそうだ。
自分の設計するときのモットーとしては、最低限まがい物は使うまいという心がけがある。そうすると使用材の中で何が本物で何がまがい物かを自分で決めなければならなくなる。
素材それ自体に優劣はない。皆本物である。それが何か別なものを模倣するとまがい物になると考える。たとえば昨今安易に使われている窯業系サイディング。それが素材のまま使われていたり保護のための塗装が施されている限りはいいけれど、例えば、タイルであるかのような仕上げを施されるとまがい物になる。「自分はタイルより格下ですが、こうするとタイルを貼ったように上等に見えませんか」。
合板についても同様なことが言える。合板自体は立派な材料であるがそれが表面に木目をプリントされていて木に見せかけていたらまがい物になる。ビニールクロスに関しても同様である。
本物とまがい物の違いは時間がたつと明瞭になる。プレハブメーカーの作る住宅はほとんどこのまがい物だけで成立しているがそこには機能だけしかない。
そんな住宅は、竣工した時が一番きれいで、あとはだんだん汚れていくばかりである。
本物を使った建物、例えば木。新築の時の香り立つ感じから時代を経て自然に色がついてきて、その間のいつの時代もよい。有名な建築家がその過程を「滅びゆく美」と言っていたがその時の英語のフレーズを思い出せないでいる。
建築家によっては、新築の時からステインで内部の木材まで着色してしまう人がいるがもったいないことだと思う。私が建物を見る際、設計者が建築をどこまで理解しているかを判断するには材料の使い方の是非を見る。
宮脇檀は「今の設計はカタログのページ数を書きこめばできてしまう」と言う様なことをいって嘆いていたが、3階にあるカタログのある「新建材(どこからをそう言うかは、個人差はあるだろうが)」は使わない、という決断も時には必要になろう。そうすると外装に使える手段・材料は限られてしまう。
たまに外壁の仕上げとして屋根と同材で同じ葺き方をしている建物を見かけるが、私と同じような考え方を持っている人が、苦肉の策で採用していると思われる。
以前は、少なくともこの大戦の前頃までは建築の材料は素材しかなかった。それを各職人が加工して建物を造った。だから技の巧拙はあっても使用材は本物しかなかった。だからまがい物の建物は出来ようがなかった。ところが幸か不幸か素材の加工技術が進歩して多彩な建材出来きてしまって、その中から自分で本物とまがい物を決めなければいけなくなっている。そうしないと材料に振り回されてしまう。
簡単である。「私がこれは本物である、といったら本物である」という自分を造ればよい。他人も納得してくれるような。それには絶えず自分を高みに置くよう磨き続けなければならないが。
そんな中でいつも判断に迷うのが“擬木”である。セメントでいかにも本物の木に見せる左官の技術の集大成。
木目模様がプリントと分かったとき、体の水分が全部吸い取られてしまうような気がするのは自分だけであろうか。多分そういった感じを持たない(持てない?)から平気で使えるのかと思う。材料に対する愛着の問題である。
ちなみに、先の深澤さんの奥田郁太郎作品は池田美術館に全部寄贈されている。

引用元:北アルプス展望美術館HP