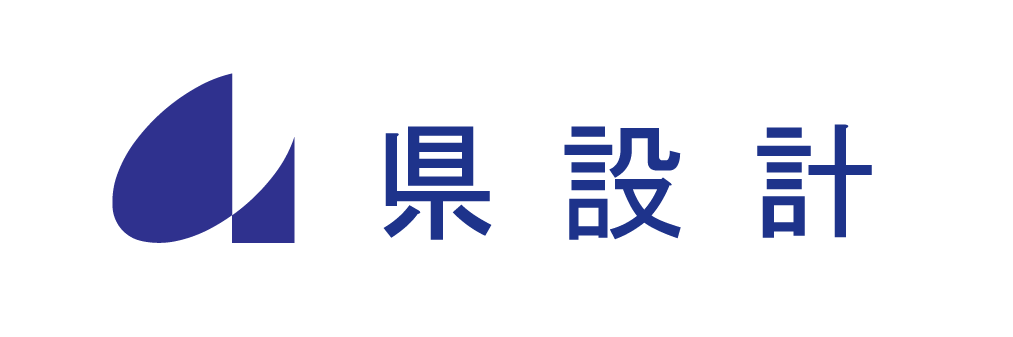都市の比較 大槻
都合郡山には都合合計11年住んでいた。36才位まで。以外は東京に1年半、その他は松本に住んでいる。都市の違い、ひいてはそれによる建築の違いについて書けという。話は長くなる。
日本などという狭い地域で地域性などは考慮するに値しないという建築家もいた。また地域性を建築に生かす、あるいは造形の手掛かりにしようとする建築家もいる。松本に来ると「アルプスに合わせて」とかは普通であるが、「フォッサマグナを意識して」と言って造った建築家もいた。
都市の比較として郡山と松本の違いを述べる。
松本に関しては皆さんがそれぞれ思っている松本として、郡山は歴史的にはほとんど戦後できた町である。両市とも昭和39年の「新産業都市」(以下、新産都市)に選ばれ国や県の投資が集中的に行われてそれから発展した町である。当時は松本も郡山も、していえば日本中が、同じような感じであった。新幹線が開通し、この前の東京オリンピックが開催されたころである。

引用元:Google Earth
地の利として東京からの距離はほぼ同じであったが郡山は早くに東北新幹線・東北自動車道が開通し、時間的には電車で東京から1時間半。松本はまだ3時間くらいかかっていたと思う。
人口については、新産都市指定頃は10万人に満たなくほぼ同じ位だった。松本は合併などで漸次人口が増えていったが、郡山は新産都市に指定されて以降外部からの流入で急激に人口が増えた、と同時に市街地の面積も増えた。かつては街はずれであった競技場が今は街の真ん中になっている。松本は20万人少しだが郡山はすぐに25万人に迫り今は30万人を超えている。
人間性について言えば松本は古い町であるからよそ者がなかなか受け入れてもらえないが、この辺は城下町の会津若松と似ている、一旦受け入れてもらえたら簡単には仲間はずれにされない。一方郡山は流入してくる人の数が圧倒的に多かったから、人と付き合うのに好き嫌いは言ってはいられない。今日知り合えばすぐ仕事をもらえたし、その代わり一寸でも気に入ってもらえなければ切られるのも早い。そんな時代だった。今は知らない。
福島県と長野県は似ている。県庁所在地は福島市と長野市。郡山と松本は一応商都と位置付けられている。人口は福島県180万人、長野県は210万一寸。松本市と福島市の人口はほぼ同じで、長野市と郡山市もほぼ同じ。面積もほぼおなじくらいで福島県は全国3位、長野県は4位。気候は郡山市の標高はおよそ250mで低いから南にあっても標高600mの松本の方が寒い。山が低いので空が広いという印象がある。果物が豊富というのは同じ。ただ、私の専門分野(?)の一つであるキノコについて言うと、長野県人が大好きなアミタケ、ジコウボウと言ったイグチ系のキノコは「毒キノコ」と言って食べない。山奥に行ってウシビテ(ウシビタイ-クロカワ)などを採ってきて正月に食べる。閑話休題。
古い建築物についていえば郡山にはほとんどない。明治15年に完成した猪苗代湖からの安積疎水(あさかそすい)が引かれてから開発された地域である。その関係の建物があったくらい。戦前からの老舗も多分1軒かせいぜい2軒。
古い建物が残るにはその地域のその時代の文化、財力が必要である。材料、工法にしっかり金をかけた建物でないと物理的に残らない。新産都市に指定されるまで郡山は貧しかった。東北自体が相対的に貧しかったと思う。
ついでの話として、池田美術館を設計する際、当時見ることのできた、主として松本から南の美術館・博物館を端から見て回ったのだが、行ったことがない県境の南。北信、中信に比べて随分開発やら道路等の整備が遅れていると思った。県内の南北格差である。日本における当時の東北も同じ。
さて、建築の話である。
正直言って今の建物に郡山と松本の違いは感じられない。自分もどちらでの設計も地域を意識したことはない。多分今はどこの県の駅前に行っても個性がない、と言われているのと同じことと思われる。昔の建物で言えば、こちらの一間は江戸間の6尺であるが福島の1間は6尺何寸であったか、畳一枚の大きさが京畳の寸法、3尺1.5寸×6尺3寸に近かった。同じ6帖でもこちらより一回り大きい。また、田舎の住宅を設計した時に「こちらでは玄関は南の中央に造る」と言われて北側が道路にもかかわらず、わざわざ南に回って入るべく玄関を南にしたこともある。プラン的には南の中央に玄関を設けるのはまとめるのが相当難しい。歴史が新しいこともあって、例えばこちらの本棟造りのような特徴的な建物はなかった。
以下は思い出話になるが、当時市の一等地に蕎麦屋を設計した。当時は郡山にきちんとした数寄屋がなかった。私のことであるから妥協せずきちんとした数寄屋で設計をした。炉も切った。それがいくつかの経過を経て土地が市の所有になって福島の有名な詩人の資料館を造ることになったという。建物を壊して新しい建物で。そこで、伝聞によると市内の建築家達から保存運動がおこったのだそうだ。そんなわけで建物は残った。しかし設計心を解ろうとしない改修設計がおこなわれていて、郡山に行った際見てつらい思いをした。

またお茶の先生から茶室を頼まれたこともあった。囲いではなく独立したものであるが、建物自体は裏千家の三帖台目下座床、普通の茶室である。主たる材料は私が自分で集めた。当時田舎に行くとまだ茅葺の家があってその解体の話を聞いては一升持っていって松の丸太の母屋をもらってくる。囲炉裏のススで真っ黒なそれを水で洗うと真っ赤な茶室の柱になる。竹は洗うと立派なスス竹に。手前畳と客畳の間に建てる中柱は稲穂を掛けるハゼ足をもらってきた。

そんな風にして造った茶室であったので、利休の心を知る、という意味で「知心庵」という名前にしていただけませんかと提案したが「湖南亭」というどうでもよい名前になったと思う。それも2~3年前に娘さんから都市計画かなんかの事情で取り壊す、という連絡があった。今は無い。