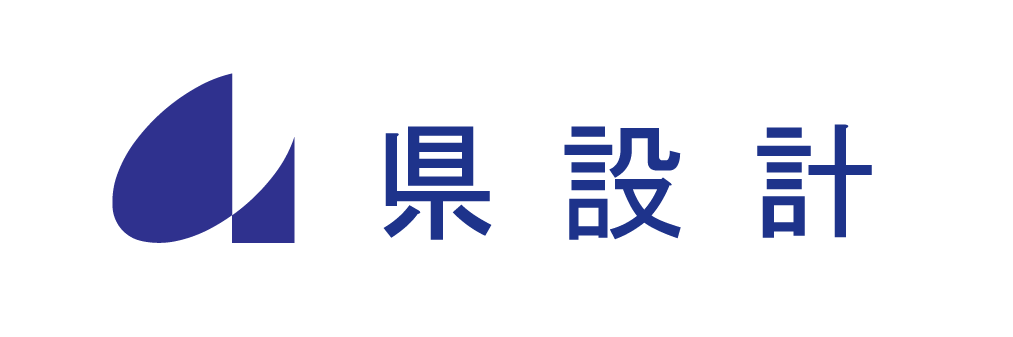センスとAIについて考える 杉山
はじめに
こんにちは。はじめまして!
所員の杉山です。
私は大学で建築を学んだ後、大学院で放棄された空地に着目し、そこに自生する雑草の植生や環境解析を通じて、人と自然を繋ぐエコロジーデザインの研究を行ってきました。その経験から、美しい自然との距離が近い暮らしを選んで、学生時代からご縁のあった県設計に入社しました!
現在は、新しいソフトや考え方を柔軟に取り入れてくれる職場のなかで、建築という長い時間をかけて完成する営みに向き合いながら日々楽しく働きつつ、学生の時の気持ちを忘れないよう休日はありのまま山か海で過ごしながら、考える日々を生きております!

上の写真は、大槻さんと山へ釣りに行った時の写真で、色々勉強させてもらいながら標高1500mくらいの場所で楽しく川登りしています!80歳でも険しいところを登るパワフルな姿を見ていると私もパワフルで在れるように鍛えねばと考えさせられます。。笑
センスってなんだろうか?
さて、建築をはじめ、生活の中で何気なく使われている「センス」という言葉。
私たちはそれをしばしば「直感」や「才能」として片付けがちですが、設計事務所という組織にいる以上ある程度共有(解釈)できるものにしたいと思いこの“センス”をより構造的に捉えることができないかと最近考えています。
ただ、新しいものにまで飛躍するような考え方の転換や完全に個人に依存したものもありますが、そこまで突き抜けたものに関しては、意識的に掘り下げられない部分があるので、一般的に使われるようなセンスについての解釈に今回はとどめます。。(高度な次元のものは追々考えていきたいっ)
今回は序文のようなものだと思って、気軽に読んで頂けたら幸いです!
仮説:「センスとは構造化された慣れの果てである」
私は、センスとは単なる直感や個人の才能だけではなく、
無意識下に蓄積された構造化された知の凝縮であり、その選択行為に意味を見出すことだと考えています。
この仮説には、以下の3つの基盤的要素の上での選択があると考えます。
1. 経験の蓄積(自己の歴史)
私たちが「これがいい」と感じる判断の多くは、過去の成功体験に根ざしています。
たとえば、「この空間は心地よい」と感じるとき、それは類似の空間で得た安心感や快適さの記憶が、無意識のうちに判断の基盤として作用しているのです。(個人に帰属するもの)
2. 社会的共有構造(社会・慣習)
センスは個人的な感性だけでなく、社会の中で繰り返され、定着してきた構造にも支えられています。
たとえば、建築のプロポーションや雑誌のレイアウトに対する「自然な良さ」は、広く共有されている文化的パターンから生じています。(社会に帰属するもの)
3. 時間的深度(遺伝子・文化 )
美的判断の背後には、進化的に獲得された感覚傾向(遺伝的要素)、文化の影響等が複雑に絡み合っています。
これは哲学でいう「深層構造」に近いものであり、判断が意識される以前から作用している可能性があります。(文化に帰属するもの)
センスとAI:大規模言語モデル(LLM)の類似性
近年注目されている**大規模言語モデル(LLM)**は、センスを構造的に捉えるための良い比喩・比較対象となると思うのです。
LLMの仕組みとセンスの類似性
LLMは、人間の膨大な言語データを学習し、そこに含まれるパターンを統計的に抽出し、重みづけを行いながら応答を生成します。
これは、個人の経験や社会的構造のなかで蓄積された知識から無意識に選択がなされる、仮説での「センス」と類似しています。
たとえば、AIの出力に対して「センスがいい」と感じることがあります。
それは、出力そのものに意図があるわけではありませんが、
私たち人間がその出力に意味を読み取り、選択的に評価しているためです。
LLMは“構造化”の過程を担当し、その出力に意味を与えるのは人間なので、LLMを利用することは、言語的には非常にポジティブに捉えられます。
センスの再定義:主観ではなく「社会的意味づけ可能性」
このように考えると、センスとは単なる主観的な直感ではなく、
社会的文脈の中で意味づけ可能な選択の出力
であると考えられますし、組織として社会・文化にとって何が必要なのかを考えるのが、共有できるものとして重要でありますね。
つまり、センスは社会的対話のなかで需給を最も満たし成立する選択なのです。
これを加速度的に考えるためにもLLMは、精査した上で共有できるものとして積極的に活用することがいいと思います。
センスと創造性──AIと人間の根本的な違い
AIは私たちが選択をするための、情報の纏め上げを担当してくれる一方で、使う間にAIに頼りっきりになってしまうのでは?とか思う人もいるでしょう。
ここで、哲学者ハンナ・アーレントの『人間の条件』を参照したいと思います。
彼女は人間の本質的能力として、“始まりを生み出す力(ナタリティ)”を挙げました。
人間は、単なる反応ではなく、「自らの意志で新しい行為を開始する力」を持っています。
AIがどれほど優れた出力を生成できたとしても、それはあくまで入力と確率的パターンに基づくものであり、意志的な創造とは異なるため、構造化して共有でき、出力も似ているものに対して、私たちは以前よりずっと批評し、意味づけを行う能力が求められ、したがってより創造性になっていくような気がしています。
組織におけるセンスの共有
そして、センス(知の凝縮と選択行為に意味を見出すこと)というのは「LLMによって知の共有」・「コミュニケーションによって選択行為に意味を見出すこと」である程度共有可能で、これが組織では重要であるような気がこの文章を書きながら改めて感じてきました。
創造性というのは、ゼロから何かを生み出すことだけでなく、他者の出力を社会的文脈の中で意味づけし、共有可能なかたちに再構成する力でもあり、これを意識的に組織だけでなく、お施主さんや協力業者の方々とも共有していければいいものが作っていける
コミュニケーションを通した意識の共有がやっぱり大事ですね!目的意識を昇華するためにも同調し過ぎずに批評しあっていられるような状態が最高です。
おわりに
まもなく30歳になる中で、LLMや生成AIによる大きな変化は間違いなく現役のうちにあると確信していて、僕らの思ういい建物とか風景なんて考えが及ばなくなるような気がしてます。
人間には意思があると話をしましたが、これはあくまでも今の段階での話で、意思の根源がそもそも何であるかなんてものは今でも明確に定義できてないので、AIが意思を持たないとは言えません。本当に人間にとって必要なものはなにかを考えてるなかで、今回のセンスの話に寄り道しました。せっかく設計事務所にいるので、組織論と繫ごうと思い書きましたが、文章とは難しいものですね。。
最後にある建築家の
「光は空間に問いを発し、空間は沈黙の中で応答する。」
なんてとても美しい詩があります。この文章を書いている時にふと思い出して、人間のセンスとか感覚みたいなものは問いと応答のあいだに立ち現れる一瞬の“光”のようなものでそれに気づけるかが重要だなと改めて思いました。
AIとの関係も、良き関係として、光が差し込む未来があると信じて、生活の場で思考を重ねて設計に落とし込んでいきたいと思います。