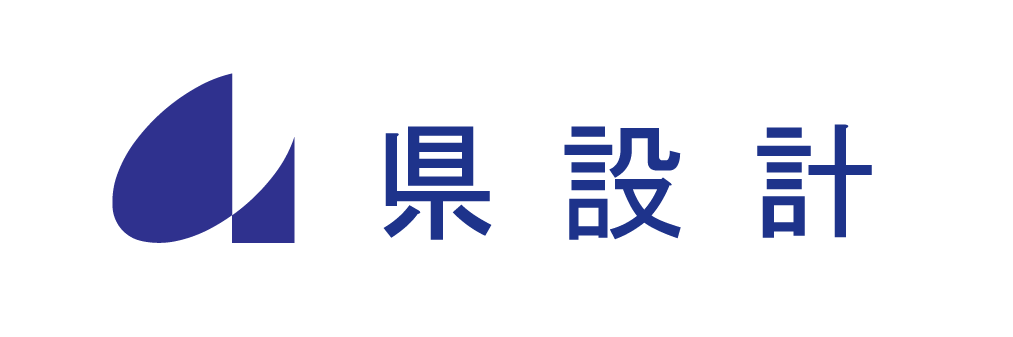景観について思うこと 篠田
こんにちは。設計部の篠田です。入社して3年目、日々の実務では先輩方のもとで建築設計に携わりながら、ホームページの管理やインターンシップの対応などにも関わらせていただいています。
社外では、「工芸の五月」に合わせて開催される〈建築家と巡る 城下町・水のタイムトラベル〉で新米として案内人を務めたり、松本都市デザイン学習会に参加したりと、立場や領域を越えてまちと向き合う場にも足を運ばせていただいてます。
そのようなご縁の中で、現在、松本市景観賞の審査委員(一般公募枠・2年任期)を務めています。今年で2年目になります。
審査委員を務めるにはまだまだ未熟な立場ではありますが、若い視点だからこそ投じられるフレッシュな意見を通じて、まちの景観づくりに貢献しながら、大きな学びの機会をいただいております。
今回は景観について考えてみたいと思います。本稿はなかなかの長文ですが、景観やまちの見え方に関心のある方に、ぜひお読みいただけたら嬉しいです。松本市景観賞に関わる中で感じてきたこと、そして建築に携わるひとりとしての私見を、率直にまとめました。
⸻
景観とは
まず「景観」という言葉にはとても広く、さまざまな解釈があると思いますが、本稿では、建築や都市という枠組みにおける景観を「まちの見栄えに対する利他的な営み」と定義してみたいと思います。
建築はしばしば、「自分たちのもの」として内向きに捉えられがちです。ですが実際には、建築は常にまちの一部として存在し、他者から見られ続けています。
「どう見えるか」「どう関わるか」を想像し、配慮すること。それが、景観をかたちづくるということだと思います。
一方で、我々設計者にとっては、施主の一世一代の想いに応えることもまた大切な責任です。まちへの配慮と、個人の夢。その両方に応えられる建築のあり方を模索するなかに、私たちが取り組むべきデザインの余地があり、技術を発揮する舞台があるのだと感じています。
⸻
景観が議論されるようになった背景
日本で「景観」が社会の議題となったのは1960年代、高度経済成長によるスクラップアンドビルドが加速し、それまで地域で育まれてきた風景が次々と失われたことが背景にあります。
1970年代には、金沢市の「まちづくり条例(1973年)」に代表されるように、住民主体の町並み保存やまちづくり運動が各地に広がりはじめます。1980年代には、京都市が全国に先駆けて景観条例を制定し、自治体レベルでの制度化が進みました。そして2004年には国による「景観法」が施行され、全国のまちで計画・規制が整備されていきます。
松本市においても早い段階から「景観賞」が設けられ、今年で第36回を迎えます。まちの風景を育てる多様な取り組みに光をあててきた、大切な制度のひとつです。
⸻
景観を考える場の意義とゆらぎ
松本市景観賞では、 建築物・工作物部門、オープンスペース部門(広場・緑地など)、まちづくり活動部門(イベントや仕組みなど)、 まちなみ部門(通りや景観全体の調和など)の4つの部門が設けられており、非常に幅広い取り組みが評価の対象になっています。
そして審査には、建築や土木の専門家だけでなく、グラフィックやランドスケープ、園芸、工芸など、多様な分野の実務者・研究者が関わっているのも特徴です。多様な観点で景観を捉え、評価する姿勢が審査会全体に宿っています。
このような長きにわたり続いている多様な観点による審査会は全国的にも珍しく、松本の良さを象徴する仕組みのひとつだと思います。
ただ、近年は応募件数の減少や制度運営の負担もあり、景観賞そのものの存続が危ぶまれているという声も耳にします。行政内部では「財源を生み出さない手間を要する制度」と見なされてしまうこともあるようです。
それでも私は、景観賞が果たしてきた役割には大きな価値があると思っています。「まちをどう見立て、どう育てていくか」という価値観を、地域全体で共有していくための営みです。その姿勢が、松本市の景観条例や景観計画の制度や実際のまちなみのかたちにも繋がっていき、まわりまわって、松本が好き。訪れたい。住みたい。という感覚を暮らしと観光、双方でもたらしていると思っています。
僕自身もその恩恵を受けた一人です。
⸻
景観と民意のあいだで
現在の松本市の景観条例では、たとえば建物外観の彩度や、看板のサイズ・設置位置に一定の基準があります。そうしたルールは、知らず知らずのうちに、私たちの日々の生活に恩恵として現れています。まちに暮らすすべての人が、少なからず“共有財産としての風景”を受け取っているのです。
ただ、景観審議会などの景観に関するルール制定の場は有識者や行政担当者によって構成されており、パブコメはあれど、市民の声が直接反映されているとは言いがたい側面もあります。
松本市中心市街地では、厳密な時期は把握しておりませんが、ある時、看板の規制が行われました。眺望を阻害する商業的で利己的なものをなるべく抑制しようという意図であったと思いますが、近頃では「看板が減って中心市街地が少し寂しくなった」と感じる声も聞かれます。逆に看板がまちのにぎわいや雑多さを演出していたのです。
規制によって統一感のある美しさが生まれる一方で、にぎわいや雑味が失われていく。そのバランスがあることについても、これからはより丁寧な対話と判断が求められていくのではないかと思います。
その点で、景観賞は誰でも応募できる仕組みを通じて、市民にとっての良い景観、民意を反映できる貴重なチャンスでもあると思いますが、一方で、実態としては、企業による広報の一環として活用されたり、「景観賞を取るためだけの営み」が見え隠れする場面もあり、少し寂しさを感じることもあります。
⸻
景観のこれから
ヨーロッパのように統一感のある街並みもあれば、渋谷のように雑多でエネルギーに満ちた景観もあります。どちらが正しい、というよりも、それぞれの地域にふさわしい「美しさ」や「豊かさ」があるのだと思います。
ただ、まちはひとつの風景の中にあります。多様な方々の意見を、「どれも正しい」としてすべてを並列に扱ってしまえば、──松本らしさ、界隈らしさ、そのまちらしさ、その道らしさ、あの場所らしさ──といった、新たな固有の風景の体得・共感覚の醸成は、かえって難しくなるのかもしれません。既存の共感覚にすがるしかなくなってしまいます。
現代において、多様性を肯定しながらも、都市やまちの景観指針は、どのように方向性を見出していくのがよいのでしょうか。
私なりの理想としては、ひとつの立場や興味のある人が勝手に決めるのではなく、全体で対話しながら折衷を探るように形づくっていくことが大切だと考えています。そのためには、まずは個々人の美意識や嗜好を表に出すこと、そして他者と交わすことが出発点だと思います。
また昨今、AIをはじめとする情報技術の発展によって、多様な価値観の集積や調整が可能な時代が来ています。誰かのひとりよがりな理想像に従うのではなく、より多くの声を可視化し、すり合わせながらかたちを探っていくことが現実味を帯びてきました。
従来では、手間や速度がかかりすぎて、間接的に一任することでしか制定することが難しかった景観の指針作りから、直接民主制のような、個々人のナラティブを損なうことのない民意の反映。多層な価値観の表出を肯定し、最大公約数を模索していくこと。これらが今後の景観づくりで技術的には可能となります。
ただ、いかに情報技術が進化し、民意の集約や解析が可能となったとしても、景観づくりの「主権」はあくまで実践者にあると思います。また、意志をもち、選び、責任を負う人が中心に立ちながらも、利害の対立による暴走を避けるために、中立的な立場にある第三者が制度設計や運用を担うような構造も望ましい気がしています。
結局のところ、どれほど技術や制度が高度化しても、制度面では現実的に大きな変化をもたらせないのかもしれません。
むしろ、制度が成熟しているからこそ、私たちが向き合う必要のあるものとしては、その中でいかに深い価値観を扱い、どれだけ質の高い対話を積み重ねていけるかという点だと思います。
例えば、「松本の山が好き」という一言にも、それが常念岳のことなのか、北アルプス全体を指すのか、朝焼けの美しさなのか、ランドマークとしての存在感なのか、あるいは自然を身近に感じられる感覚なのか――言葉は似ていても、人によってその背景やニュアンスはまちまちです。
通じ合っているようで、実はそうではなくて、本質的な内側からの共感が生まれてこず、どこへ行っても一般解の共有で止まってしまうのではないでしょうか。だからこそ、あえて深い部分を言葉にし、互いに表に出してみることが大事だと思います。
そして、最終的には、より深い共感を持った魅力的なナラティブを紡ぎだせるかどうか。それがヒトの営みの枠組みの中で、個人レベルでも、組織や地域という単位においても、景観づくりの根幹を左右していくのではないかと考えています。
⸻
利己(ウチ)と利他(ヨソ)を調停する景観
うちはウチ、よそはよそ。なるべくその境界ははっきりさせたい。そんな感覚が当たり前だった時代から、今は少しずつ変わりはじめています。シェアすること、まちに開くこと、つながろうとする人が増えてきた時代でもあります。
とはいえ、現代においても──「なんでよそのためにそこまでしなきゃいけないのか。」「調和よりも、目立つ方が大事だ」というように、ウチのためにヨソを排除していくような、土地・建物の占有感覚が先に立ってしまうことも、やはりあると思います。
人類学者のフランス・ドゥ・ヴァールなどの研究によれば、人間は「ゴリラ的な家族愛」と「チンパンジー的な社会性」の両方を兼ね備えた動物だとされています。一対一の深い関係を大切にしながらも、血縁を越えた複雑な社会構造を築き上げる。それが、元来の人の特徴だそうです。
「家か、仕事か」のように、ゴリラ的なウチ性とチンパンジー的なヨソ性がぶつかり合う場面も多くあります。
人はそういった性質から、基本的にはウチを大事にしながらも、どこかで「ヨソからどう見られるか」を気にしている生きものだと思います。とはいえ、日常の中でその意識が常に働いているわけではなく、また、ヨソへの射程は近く、実際にはごく身近な数十人、せいぜい150人程度までに限られているそうです。(「150人前後」という数字は、人やチンパンジーが社会的に認知できる関係数の上限とも言われています。)
だからこそ、実態の「社会全体」「景観全体」といったものを、日々の暮らしのなかでリアルに実感するのは、正直かなり難しいと思います。スマホで見ている社会も、すごく偏っているので、現代におけるいわゆる“多様性感覚”も、どこか極端なマイノリティ偏向で迷走しているような気もしますし、偏らないことは難しいとも思います。
解釈がとてもあやふやな中で、「万人のための景観なんて」と思ってしまう感覚も、僕自身まったく持っていないとは言い切れません。逆に、社会の“正しさ”を装った同調圧力によって、個々人の「うちはウチ」という感覚まで失われてしまえば、誰のための社会でもない、ただ息苦しいだけの社会になってしまうんじゃないか──という思いもあります。
「ウチ」と「ヨソ」の”あわい(向かい合うものの間の関係)”。この感覚は景観に限らず、多くの人が日常的に感じているものかもしれませんが、景観をめぐる葛藤の根源も、まさにこの個人・家族(ウチ)、そして社会(ヨソ)の感覚のバランスにあるように思います。
ウチとヨソを二項対立的に捉えるのではなく、そのあいだにある葛藤に向き合いながら、シームレスにつながる部分を探していく営みこそが、利己と利他の双方に資する、本質的な「見栄え」=景観づくりにつながるのではないかと考えています。
たとえば、「本当は緑でいっぱいにしたいけれど、管理が大変だ」「開放的な施設にしたいけれど、プライバシーは守りたい」
「青色が好きだけれど、地域になじむ色味にも配慮したい」──そうした日常に潜む葛藤の先にこそ、単なるキッチュな見てくれではない、ナラティブのある本質的な景観づくりが広がっていると思います。
私自身、そうした思いに応えられるように、魅力あるデザインを通じて景観に資する建築を目指し、日々の実践を重ねながら、学びと研鑽を深めていきたいと考えています。
⸻
今回はこの場をお借りして、率直に景観についての私なりの考えを述べさせていただきました。
とても長い文章になってしまいました。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
ご参考になりましたら幸いです。
なお、今年度の松本市景観賞は6月30日(日)まで応募を受け付けています。
応募者には先着で、歴代受賞作で遊べる景観かるたももらえます。ぜひご応募ください。
松本市景観賞募集に関してはこちら